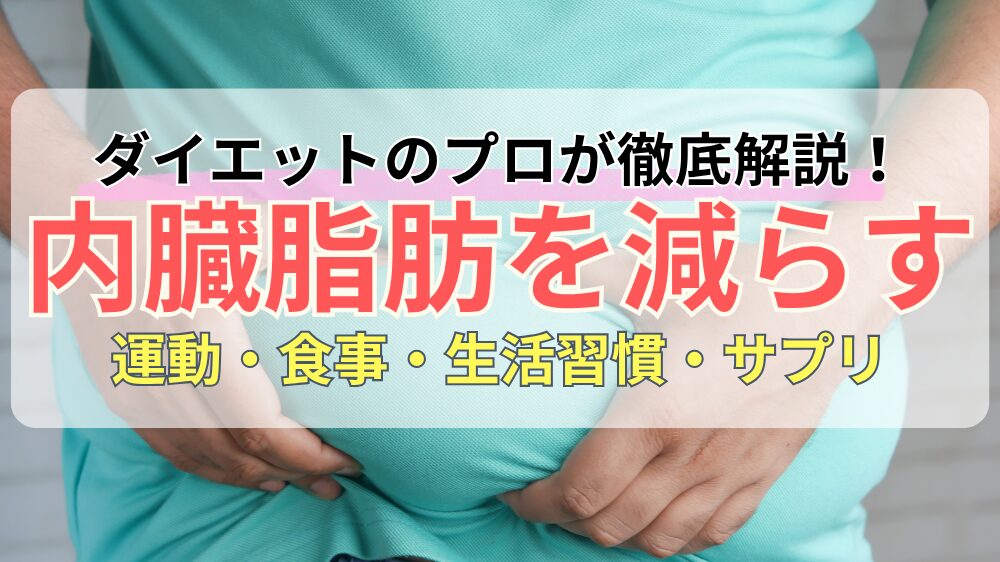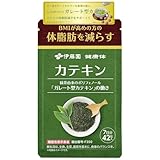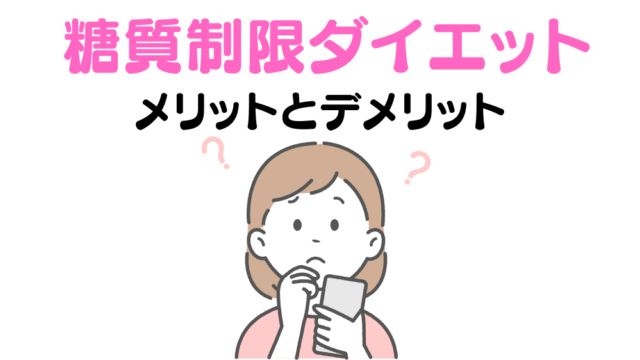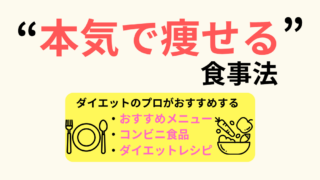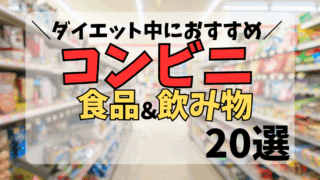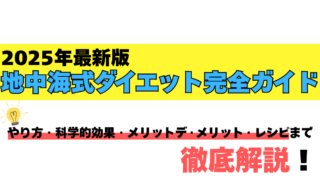年齢を重ねると、「お腹まわりだけなかなか落ちない」「体重は同じでもズボンがきつくなった」と感じる方が増えます。
それはもしかしたら「内臓脂肪」のサインです。
内臓脂肪は見た目以上に健康を害するリスクが高く、放置すると糖尿病・高血圧・脂質異常症・動脈硬化など生活習慣病を引き起こす可能性があります。
一方で、正しい方法で生活習慣を整えれば、内臓脂肪を減少させて2〜3ヶ月で目に見える変化を実感することも可能です。
本記事では、医学的な根拠とともに「内臓脂肪を減らすための運動・食事・生活習慣の整える方法」を解説します。
この記事を最後まで読めば、健康的に、リバウンドせずに内臓脂肪を減らす正しい方法がわかります。
この記事を読むことで、以下の悩みを解決できます。
- ダイエットしてもお腹だけ痩せない
- 健康診断で内臓脂肪レベルが高いと指摘された
- 効果的な運動・食事法を知りたい
- 無理せず長く続けられる方法を知りたい
本気で痩せたいあなたへ

本気で痩せて人生を変えたい方には、
2000円~のオンラインのダイエットサポートもおすすめしています詳細は下のボタンから!
- 食事管理などすべて丸投げでOK!
- 一人一人に合ったダイエットプランで毎日徹底サポート!
- オンラインだから全国どこでもOK!年齢や性別も関係なし!
本気で身体を変えたいあなたへ
オンラインボディメイクサポート

細マッチョを目指したい男性、スリムで女性的な体型を目指したい女性の方などボディメイクに挑戦したい方向けにもオンラインでパーソナルボディメイクも受け付けています!
内臓脂肪とは?
内臓脂肪とは?
内臓脂肪とは、腹部の内臓の周囲(肝臓や腸のまわりなど)に蓄積する脂肪のことを指します。
見た目には分かりにくいものの、体の内側にたまるため「隠れ肥満」とも呼ばれ、健康に大きな影響を与える脂肪として注目されています。
一方で、皮膚のすぐ下につく脂肪は「皮下脂肪」と呼ばれ、見た目の体型に関係します。
まずは、この2つの違いを明確に理解することが、内臓脂肪を減らす第一歩です。
内臓脂肪と皮下脂肪の違い
脂肪には「内臓脂肪」と「皮下脂肪」の2種類があります。
内臓脂肪は、エネルギーの貯蔵庫としての働きが強く、過剰にたまると体に悪影響を及ぼします。皮下脂肪は、体を保護したり体温を維持したりする役割があります。
特に男性は内臓脂肪がつきやすく、女性は皮下脂肪がつきやすい傾向があります。
| 種類 | 溜まる場所 | 特徴 | 落ちやすさ |
|---|---|---|---|
| 内臓脂肪 | 腹腔内(内臓まわり) | 男性に多い。見た目に出にくいが健康リスク高い | 落ちやすい |
| 皮下脂肪 | 皮膚のすぐ下 | 女性に多い。見た目に出やすく落ちにくい | 落ちにくい |
内臓脂肪は、体の中心部に蓄積するため内臓機能を圧迫し、ホルモンバランスを乱す原因になります。一方で、正しい方法で生活習慣を変えれば比較的早く落とせる脂肪でもあります。
内臓脂肪が健康に及ぼす影響
内臓脂肪が増えると、見た目だけでなく健康リスクが急上昇します。
その理由は、内臓脂肪が「ホルモンのように働く有害物質」を分泌するためです。
内臓脂肪が健康に及ぼす影響は、以下のような影響があります。
- インスリンの働きを妨げ、糖尿病リスクを上げる
- 血中の悪玉コレステロール(LDL)を増やす
- 高血圧や脂質異常症を引き起こす
- 慢性的な炎症状態をつくり、動脈硬化を進行させる
これらは「メタボリックシンドローム」と呼ばれ、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる疾患の引き金になります。
そのため、見た目に太っていなくても内臓脂肪が多いというケースは少なくありません。
また、最新の研究では、内臓脂肪の蓄積が「がん」「認知症」「睡眠障害」といった慢性疾患のリスクにも関与していることが示唆されています(国立健康・栄養研究所などの報告より)。
つまり、内臓脂肪を減らすことは見た目のためだけでなく、健康寿命を延ばすための重要な取り組みなのです。
内臓脂肪がつきやすい人の特徴
内臓脂肪は、誰にでもつく可能性がありますが、特につきやすい体質や生活習慣があります。以下の特徴に心当たりがある場合は、注意が必要です。
内臓脂肪がつきやすい人の特徴
- 食事が早食い・大食い・外食中心
- 炭水化物や脂っこいものを好む
- 運動習慣がない(デスクワーク中心)
- 睡眠時間が短い、または不規則
- ストレスを感じやすい
- 40歳以降で基礎代謝が低下している
加齢とともに筋肉量が減ると、消費エネルギーも減少しますので、年齢が若い頃と同じ食事量でも内臓脂肪が増えやすくなります。
特に男性では30代後半から、女性では更年期以降に急増する傾向があるため、早めの対策が大切です。
内臓脂肪レベルの測定方法
自分の内臓脂肪量を簡単に知るには、「ウエスト周囲径」を測るのがおすすめです。
男性85cm以上、女性90cm以上が内臓脂肪型肥満の目安とされています(厚生労働省の基準より)。しかし、より正確に知りたい場合は以下のような方法もあります。
- CTスキャン検査:最も正確。医療機関で実施可能。
- 体組成計(内臓脂肪レベル付き):家庭でも簡単にチェックできる。
- BMIとの併用:BMI25以上かつウエスト増加は要注意。
最近では、家庭用の高精度体組成計でも「内臓脂肪レベル」を数値化できるものが増えています。
定期的に測定し、数値の変化を確認しながら生活習慣を改善していくことが、内臓脂肪対策につながります。
内臓脂肪が増える原因
内臓脂肪は、気づかないうちに少しずつ蓄積してしまいます。
食べすぎや運動不足だけでなく、睡眠の質やストレス、加齢といった日常の小さな要因が積み重なることで、内臓まわりに脂肪が増えてしまうのです。
ここでは、内臓脂肪が増える主な4つの原因を詳しく解説します。
食生活の乱れ
内臓脂肪を増やす最大の要因は「糖質」と「脂質」の過剰摂取です。
現代の食生活では、コンビニ食や外食に頼る機会が多く、無意識のうちに高カロリー・高脂質の食事を摂ってしまいがちです。
特に以下のような食習慣は、内臓脂肪を増やす代表的な原因となります。当てはまる人は、まずはできる範囲で食習慣の改善を始めましょう!
- 白米・パン・麺類などの炭水化物中心の食事
- 揚げ物・ジャンクフード・スイーツの頻繁な摂取
- 夜遅い時間の食事(22時以降)
- アルコールの飲みすぎ(特にビールや日本酒)
上記のような食事は血糖値を急上昇させ、インスリンの分泌を促進します。
インスリンは血糖を下げる働きがありますが、同時に「脂肪をため込むホルモン」でもあるため、過剰に分泌されると内臓脂肪の蓄積を加速させてしまいます。
また、糖質と脂質を同時に多く摂取すると、余分なエネルギーが中性脂肪として肝臓や内臓まわりにたまりやすくなります。
特に夜遅い食事は、エネルギー消費が少ない時間帯に摂取するため、脂肪として蓄積されやすく注意が必要です。
運動不足
もう一つの大きな原因が「運動不足」です。
デスクワーク中心の生活では、1日の消費カロリーが少なく、摂取エネルギーが余りやすくなります。
余ったエネルギーは体脂肪として蓄積され、特に内臓の周囲に集まりやすい傾向があります。
また、運動不足は筋肉量の減少を招きます。
筋肉は基礎代謝(何もしなくても消費されるエネルギー)の約20%を占めており、筋肉が減ると代謝が下がり、結果的に内臓脂肪が燃えにくい体質になります。
このようなエネルギー消費の低下と脂肪蓄積が重なることで、内臓脂肪がどんどん蓄積していく悪循環を生むのです。
さらに、通勤・買い物などで歩く機会が減ったことも、内臓脂肪増加の一因です。
日常生活の中で「歩く・階段を使う」などの小さな運動習慣を意識するだけでも、内臓脂肪の増加を防ぐ効果が期待できます。
睡眠不足・ストレス
意外かもしれませんが、睡眠不足や慢性的なストレスも、内臓脂肪を増やす大きな要因となります。その背景には「ホルモンバランスの乱れ」があります。
睡眠が不足すると、体内で「コルチゾール」というストレスホルモンが過剰に分泌されます。
コルチゾールは血糖値を上げる働きを持ち、余ったエネルギーを脂肪として蓄積させてしまいます。
さらに、睡眠不足は「レプチン(満腹ホルモン)」を減少させ、「グレリン(食欲促進ホルモン)」を増加させるため、無意識のうちに食欲が増していきます。
慢性的なストレスも睡眠不足と同様に、交感神経を優位にして、食べすぎや甘いものへの欲求が高まります。
ストレスによる“やけ食い”や“夜中の間食”が習慣化してしまうと、短期間でも内臓脂肪が急増する可能性があります。
そのため、質の良い睡眠をとること、ストレス発散は、内臓脂肪対策と言えます。
加齢による代謝低下
40代以降になると、「同じ生活をしていても太りやすくなった」と感じる方が増えます。
これは、加齢によって筋肉量やホルモン分泌が減少し、基礎代謝が下がるためです。
結果として、若い頃と同じ食事量でもエネルギーが余りやすくなり、内臓脂肪がつきやすくなるのです。
特に男性では「テストステロン(男性ホルモン)」の減少が、脂肪の蓄積や筋肉量の減少に直結します。
女性の場合は、更年期以降に「エストロゲン(女性ホルモン)」が急激に減少し、脂肪が内臓に集中して蓄積されやすくなります。
また、年齢を重ねるとともに活動量が自然に減ることも、脂肪増加の原因となります。
しかし、筋トレやウォーキングなど運動習慣を継続することで、筋肉を維持すれば加齢による代謝低下を大幅に抑えることが可能です。
効果的に内臓脂肪を減らす運動方法
内臓脂肪を効率的に減らすためには、「有酸素運動」と「筋トレ」をバランスよく組み合わせることが重要です。
食事制限だけで内臓脂肪を落として一時的に体重が落ちても、筋肉が減り、リバウンドしやすい体になってしまいます。
食事管理にプラスして運動を取り入れることで「脂肪を燃やしやすい代謝の高い体」を作ることができ、内臓脂肪に効果的です。
有酸素運動
内臓脂肪は、酸素を使って分解・燃焼される性質があります。
そのため、ウォーキングやジョギングなどの「有酸素運動」が効果的です。
効果的に脂肪燃焼する有酸素運動は、少し息が弾む程度の中強度運動です。
これにより、体内の脂肪が主なエネルギー源として使われやすくなります。
具体的には以下のような運動がおすすめです。
- ウォーキング(1日30分以上、週5回)
- ジョギング(ゆっくりペースでOK)
- サイクリング(有酸素運動+下半身強化)
- 水泳・アクアウォーキング(関節への負担が少ない)
- エアロビクスやダンス(楽しみながら脂肪燃焼できる)
厚生労働省「健康づくりのための運動指針2024」によると、
週150分以上(1日30分×週5日)の有酸素運動を行うと、2〜3か月で内臓脂肪が15〜20%減少する効果が報告されています。
さらに、1回30分まとめて運動できない場合でも、
「10分×3回」のように小分けにしても同等の効果が得られることがわかっています。
つまり、通勤中の徒歩や買い物などの日常で出来る有酸素運動でも十分に脂肪を減らすことが可能なのです。
筋トレ
内臓脂肪を落とすには、筋トレ(無酸素運動)も欠かせません。
筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、1日の消費カロリーが自然に増えます。
つまり、“運動していない時間”にも脂肪が燃えやすくなるのです。
特に大きな筋肉(大腿四頭筋・背筋・胸筋)を鍛えることで、エネルギー消費や脂肪燃焼効果が効率化します。
おすすめの自宅トレーニングメニュー
- スクワット:下半身と体幹を同時に鍛える
- プランク:お腹周りのインナーマッスルを引き締める
- 腕立て伏せ:上半身+体幹を強化
- ヒップリフト:お尻・太もも裏の筋肉を刺激
1日10〜15分でも継続することで、基礎代謝が徐々に上がり、脂肪燃焼効率がアップします。
また、筋トレ後に有酸素運動を組み合わせると、より内臓脂肪を減らす効果が高まります。その理由は、筋トレによって分泌される「成長ホルモン」や「アドレナリン」が、
体脂肪分解を活性化し、有酸素運動中の脂肪燃焼効率を大幅に高めてくれるためです。
日常生活でできる「ながら運動」
忙しくて運動の時間が取れない人は、日常の動きを少し工夫するだけでもOKです。
- 通勤時に1駅分多く歩く
- エスカレーターではなく階段を使う
- 歯磨き中にかかと上げ(カーフレイズ)
- 家事中にお腹を引き締める意識
- デスクワーク中に腹式呼吸を意識
こうした“小さな運動の積み重ね”が、1日100〜200kcalの消費につながり、
長期的には数kg単位の脂肪減少に結びつきます。
脂肪燃焼を高める時間帯と「ペース」
朝食前の空腹時は、体内の糖が少なく、脂肪をエネルギー源として使いやすい状態です
そのため、朝食前の空腹時にウォーキングや軽いジョギングは、効果的に脂肪燃焼が可能です。また、朝の運動は1日の代謝を上げる効果も期待できます。
また、長時間の有酸素運動は、体脂肪を分解するホルモン「カテコールアミン」や「成長ホルモン」の分泌を促進してくれるので、結果として脂肪燃焼に効果的です。
ただし、起きたばかりの状態でいきなりハードな運動を行うと疲労やケガの原因になるため、まずは「息が弾むが会話はできる程度」の軽めの運動から始めて、徐々に運動時間や強度を伸ばしていくことが大切です。
有酸素運動や筋トレを続けるためのコツ
運動習慣で一番大事なのは継続することです。
下記のようなコツや工夫をして運動習慣を続けましょう!
有酸素運動や筋トレを続けるためのコツ
- 最初から完璧を目指さず、まずは無理なくできる範囲でOK!
- 音楽やオーディオブックを聴きながら、楽しく行う
- 運動後にお気に入りのプロテインドリンクを楽しむ
- スマートウォッチやアプリで運動の成果を見える化して後で見返す
内臓脂肪を減らす食事
内臓脂肪を効率的に落とすためには、「何を食べるか」も大事ですが、「どのように食べるか」も非常に重要になってきます。
短期間で結果を出すには、極端な食事制限ではなく、代謝を落とさず脂肪を燃やす食習慣を身につけていることです。
ここでは、科学的根拠に基づいた「脂肪をためない・燃やす食事法」を紹介します。
脂質制限
内臓脂肪の最大の原因のひとつが、「脂質」の過剰摂取です。
揚げ物・バター・スナック菓子・加工肉(ソーセージ・ベーコンなど)等の食品は、体内で中性脂肪に変わりやすい飽和脂肪酸やトランス脂肪酸が多く含まれています。
肝臓で処理しきれなかった脂質は内臓周囲に蓄積され、脂肪肝や内臓脂肪型肥満の原因となります。
しかし、完全に脂質をカットするとホルモンバランスが乱れ、逆に代謝が落ちてしまうため、「悪い脂質を減らし、良質な脂質を摂る」ことがポイントです。
良質な脂質とは、以下のような“オメガ3脂肪酸”を多く含む食品です。
これらは中性脂肪を減らし、脂肪燃焼を促進するEPA・DHAを豊富に含みます。
実際に、EPAを多く摂取している人は、内臓脂肪の蓄積リスクが低いという研究報告もあります。
オメガ3脂肪酸を多く含む食品
- 青魚(サバ・イワシ・サンマなど)
- アマニ油・えごま油
- くるみ・アーモンド
タンパク質を意識して摂る
ダイエット中は、筋肉を減らさないために「タンパク質」をしっかり摂ることが大切です。
筋肉量が維持されることで基礎代謝が保たれ、脂肪が燃えやすい状態をキープできます。
さらに、タンパク質に注目するだけでなく、下記のような、「高タンパク低脂質」な食品を選びましょう!
おすすめの高タンパク低脂質食品
- 鶏むね肉・ささみ
- 卵・豆腐・納豆
- ギリシャヨーグルト
- 魚介類(特に白身魚・ツナ)
1日の摂取目安は「体重×1.2〜1.6g」が理想です。
例えば体重60kgなら1日70〜90gのタンパク質を目標にしましょう。また、食事のたびにタンパク質を分けて摂ると、筋肉合成が効率的に進み、内臓脂肪の減少に効果的です。
腸内環境を整える「発酵食品」と「食物繊維」
近年の研究では、「腸内環境」と「内臓脂肪」は密接に関係していることが明らかになっています。
腸内の悪玉菌が優勢になると、炎症やインスリン抵抗性が起こりやすくなり、脂肪が蓄積しやすい体質になってしまいます。そのため、腸内環境を整える食事は内臓脂肪を減らす食事とも言えます。
おすすめは、以下のような発酵食品や食物繊維を多く含む食材です。
腸内環境を整えるおすすめ食材
- 発酵食品:納豆、キムチ、ヨーグルト、味噌
- 水溶性食物繊維:オートミール、海藻、アボカド
- 不溶性食物繊維:野菜、きのこ、豆類
これらを組み合わせることで腸内フローラが改善し、脂肪燃焼を促進する「短鎖脂肪酸(酪酸など)」が増加します。
さらに脂肪燃焼効果以外にも、便秘解消・むくみ軽減・代謝アップなど、複合的なダイエット効果を得ることができます。
内臓脂肪を減らすための食ベ方のコツ
- 朝食を抜かない:朝食を食べることで体温と代謝が上がり、1日のエネルギー消費が高まります。そのため、その日の食事が脂肪として蓄積されにくくなります。プロテインや卵、オートミールなどを朝に摂ると脂肪燃焼スイッチがONになります。
- 夕食は就寝3時間前までに摂る:寝る直前の食事は、消費されずに内臓脂肪として蓄積されやすいです。どうしても食事が夜遅くなる場合は、消化の良いスープや豆腐、野菜中心にしましょう。
- よく噛んでゆっくり食べる:満腹中枢が刺激されるまでに約20分かかるため、早食いは食べすぎの原因に。 ゆっくり食べることで血糖値の上昇も緩やかになります。
- 食べる順番を工夫する:「食物繊維 → タンパク質 → 炭水化物」の順に食べると、糖質の吸収が穏やかになり脂肪蓄積を防げます。
避けるべき食品とその理由
内臓脂肪をためる食習慣を断ち切るためには、「控えるべき食品」を明確にしておくことも重要です。
特にアルコールは「脂肪合成ホルモン(インスリン)」の分泌を促進するため、週2回以上の多量摂取は内臓脂肪を蓄積させやすいことが分かっています。
飲む場合は、蒸留酒(焼酎・ウイスキー)を少量にし、枝豆や冷奴など高タンパク・低脂質のおつまみを選びましょう。
控えるべき食品
- 清涼飲料水・ジュース類:砂糖が多く、血糖値を急上昇させる
- 菓子パン・スイーツ:トランス脂肪酸と精製糖のダブルパンチ
- 加工食品・カップ麺:塩分・脂質が多く、むくみや代謝低下を招く
- アルコール:肝臓がアルコール分解を優先するため、脂肪燃焼がストップ
内臓脂肪を減らす生活習慣とメンタルケア
内臓脂肪を減らすために、運動や食事を意識する人は多いですが、実は「生活習慣」と「メンタル管理」も大きな鍵を握っています。
睡眠・ストレス・アルコール・喫煙などの習慣は、ホルモンバランスや代謝に直接影響を与え、努力の成果を左右します。
つまり、生活リズムを整えることが、内臓脂肪を自然と燃やしてくれる“痩せ体質”をつくるために必要な要因となります。
ここでは、科学的根拠に基づいた生活習慣の改善ポイントと、心を整えるメンタルケアの方法を紹介します。
質の良い睡眠で脂肪を燃やす体をつくる
科学的にも「寝ている間に脂肪は燃える」ということがわかっています。
睡眠中、体では成長ホルモンやメラトニンが分泌され、細胞修復や脂肪分解が活発に行われます。
逆に前述した通り、睡眠不足になると、食欲を増進させる「グレリン」が増え、食欲を抑える「レプチン」が減少し、食べ過ぎの原因となってしまいます。
理想的な睡眠時間は7時間前後。特に22時〜2時の間は「脂肪分解ホルモン」が最も活性化するゴールデンタイムと呼ばれ、この時間帯に深い睡眠を取ることが大切です。
良質な睡眠を得るためのポイント
- 就寝2〜3時間前に食事を済ませる
- 寝る前のスマホ・PCを控える(ブルーライトはメラトニン分泌を妨げる)
- 寝室を21〜23℃に保ち、暗く静かな環境を整える
- 寝る前に軽くストレッチや腹式呼吸を行う
睡眠の質を整えるだけで、食欲ホルモンのバランスが改善され、自然と間食が減る人も多くいます。
ストレスを味方につけるメンタルケア
「ストレス太り」という言葉があるように、精神的な緊張や不安は内臓脂肪の増加と深く関係しています。ストレスを受けると副腎から「コルチゾール」というホルモンが分泌され、これが脂肪をため込む信号を出します。
特にダイエット中はストレスが溜まりやすく、根本的に無くすことは難しいですが、「溜めない工夫」をすることでホルモンバランスを保てます。
ダイエット中のストレス軽減法
- 1日10分のウォーキングでリセット
- 深呼吸や瞑想を取り入れる(副交感神経を活性化)
- アロマや音楽でリラックス環境をつくる
- 誰かに話す・書き出す(感情の整理になる)
近年では、軽い運動と瞑想を組み合わせた「マインドフルフィットネス」が、ストレス性肥満の改善に効果があるという研究結果もあります。
アルコールとの上手な付き合い方
体内に入ったアルコールは、まず肝臓で分解されますが、この過程で脂肪の代謝が一時的に止まってしまいます。
さらに、アルコールには食欲を刺激する作用があり、飲酒後につい食べすぎてしまう原因こ。
とはいえ、完全に禁酒するのが難しい人も多いと思います。
そんな方は、アルコールの量を減らすだけでも、2〜3週間で体脂肪率に変化が出るケースもあります。
またお酒を飲む際は、以下のルールを守るだけでも脂肪の蓄積を抑えられます。
内臓脂肪をため込まないお酒のルール
- 飲む頻度は週2回以内に
- 焼酎・ウイスキーなど糖質ゼロの蒸留酒を選ぶ
- ビールやカクテルは控えめに
- おつまみは枝豆・冷奴・チキンサラダなど高タンパク低脂質に
禁煙で内臓脂肪の蓄積を防ぐ
喫煙は内臓脂肪の蓄積と強く関係しています。
ニコチンが血管を収縮させ、血流を悪化させることで、脂肪が酸化・燃焼しにくい状態になるためです。
また、喫煙はホルモンバランスを乱し、男性ではテストステロン、女性ではエストロゲンの分泌を低下させます。
これらのホルモンは筋肉量維持や脂肪代謝に関与しているため、喫煙習慣は代謝低下を招く原因にもなります。
また、禁煙によって血流が改善し、体温・代謝が上がることで、脂肪燃焼効率が向上することも報告されています(日本循環器学会 2024)
内臓脂肪を減らすサプリメント活用法
内臓脂肪を減らすための基本は、あくまで「食事」「運動」「睡眠」の3本柱です。しかし、これらを意識的に続けていても、「なかなか効果が実感できない」「年齢とともに脂肪が落ちにくくなった」と感じる人もいるかもしれません。
そんなときにサポート役として取り入れたいのが「サプリメント」です。
サプリによって代謝・腸内環境・ホルモンバランスを整えることで、内臓脂肪の減少をサポートしてくれます。ここでは、医学的根拠や研究報告のある有効成分を中心に、サプリの正しい選び方と活用法を解説します。
しかし、注意してほしいのは、サプリは魔法のように脂肪を溶かすものではありません。
あくまで内臓脂肪を減らすサポートとして活用しましょう。
また、サプリを複数併用する際は、成分の重複にも気をつけましょう。
例えば、脂肪燃焼系サプリに含まれるカフェインやカルニチンを過剰に摂ると、心拍数や血圧が上がるリスクがあります。
不安がある場合は、医師や管理栄養士に相談するのが安全です。
L-カルニチン(脂肪燃焼を助ける栄養素)
L-カルニチンは、脂肪酸を「ミトコンドリア」に運び、エネルギーとして燃やす働きを持つ成分です。つまり、脂肪を「燃焼できる状態」に導くサポートをする働きがあります。。
加齢とともに体内のL-カルニチン量は減少するため、40代以降はサプリメントからの補給が有効です。
実際に、米国の研究(Journal of Physiology, 2011)では、L-カルニチンの摂取により筋肉内の脂肪代謝効率が向上し、体脂肪率が減少したとの報告もあります。
EPA・DHA(青魚に多いオメガ3脂肪酸)
上記で紹介した青魚に含まれる脂肪燃焼効果のある「EPA」と「DHA」はサプリでも摂ることができます。
これらのオメガ3脂肪酸は、血中中性脂肪を下げ、内臓脂肪の蓄積を防ぐ働きが報告されています。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」でも、EPA・DHAの摂取は生活習慣病予防の観点から推奨されています。
また、EPAには「脂肪燃焼を促進するホルモン(アディポネクチン)」の分泌を増やす作用があり、代謝を高める効果も期待できます。
難消化性デキストリン・乳酸菌(腸内環境を整える)
腸内環境の悪化は、内臓脂肪の増加と深く関係しています。
近年の研究では、「腸内細菌が肥満を左右する」ことが明らかになっており、特に“悪玉菌の増加”は脂肪蓄積を促進する要因とされています。
そのため、腸活サプリとして人気なのが「難消化性デキストリン」や「乳酸菌」「ビフィズス菌」。これらは腸内フローラを整え、脂肪吸収を抑えるだけでなく、食後の血糖値上昇をゆるやかにする働きもあります。
特に難消化性デキストリンは、特定保健用食品(トクホ)にも多く採用されており、継続的に摂ることで内臓脂肪が減少したという報告も存在します(花王研究所, 2019年)。
ブラックジンジャー・カテキン(脂肪燃焼を促進)
「ブラックジンジャー」には、脂肪分解酵素を活性化させ、エネルギー消費を高める作用があります。タイの伝統医学では滋養強壮成分として知られており、近年では“脂肪燃焼素材”として機能性表示食品にも多く採用されています。
「カテキン(特にガレート型)」には、脂肪の吸収を抑制し、運動時の脂肪燃焼率を高める作用があります。
これらを組み合わせることで、運動による脂肪燃焼効率をさらにアップさせることができます。
まとめ
今回は内臓脂肪の減らし方について、「食事」「運動」「生活習慣」「サプリ」の観点からご紹介しました!
内臓脂肪は運動不足や食べ過ぎだけでなく様々な要因で増えてしまいます。
健康診断で内臓脂肪が多いと診断された方や、最近体型が気になる方はぜひ参考にしてください!
また、オンラインのダイエットサポート、ボディメイクサポートも行っているので、
痩せたい方や体型を変えたい方はぜひチェックしてみて下さい!
オンラインダイエットサポート

\【期間限定】1か月3000円!/
・食事管理などすべて丸投げでOK!
・一人一人に合ったダイエットプランで毎日徹底サポート!
・オンラインだから全国どこでもOK!年齢や性別も関係なし!