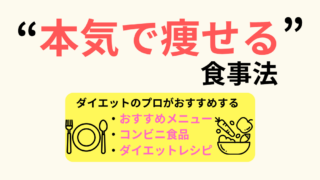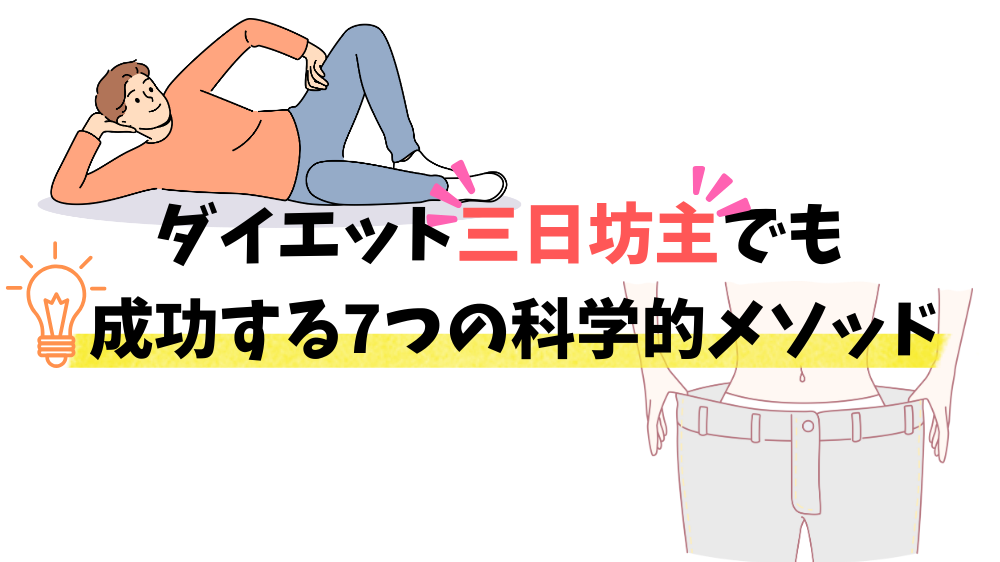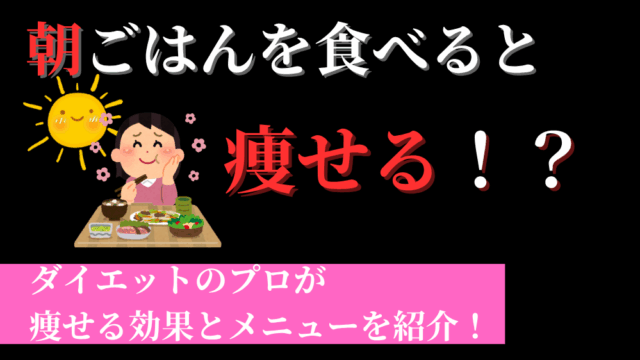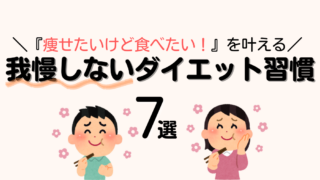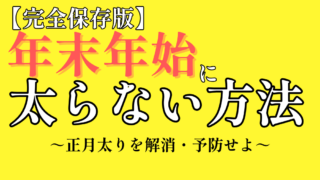「またダイエット、続かなかった…」そんな自己嫌悪に陥っていませんか?
実は、ダイエットの挫折率は87%(※日本健康調査研究センター調べ)。
多くの人が「意志が弱いから」「自分には向いていないから」と諦めてしまいますが、それは間違いです。続かないのは“あなたの性格”ではなく、“脳と環境の仕組み”のせいです。
本記事では、心理学・脳科学・行動経済学の研究をもとに、
「なぜダイエットは続かないのか?」
「どうすれば三日坊主でも成功できるのか?」を科学的に解説します。
💡この記事を読むことで以下の3つが身に付きます!
- 続かない原因が“自分のせいではない”と理解できる
- 科学的に正しい“続ける技術”が身につく
- 明日から行動できる“7つの実践法”がわかる
いつもダイエットを挫折してしまうあなたへ

💡「いつもダイエットが続かない」「リバウンドとダイエットを繰り返してしまう。」そんな方には、1週間から出来るダイエットサポートがおすすめです!
オンラインダイエットサポート
- オンラインだから全国どこでもサポート!
- あなた専用の効率的ダイエットプランで理想の体に!
- ダイエットの専門家が毎日徹底サポート!
詳しくはこちら👉
なぜダイエットは続かないのか
挫折率は87%、平均継続期間は「3週間」
厚生労働省の調査(2024)によると、ダイエットを始めた人の87%が3ヶ月以内に挫折しています。
特に「1週間で断念」が25%、「1ヶ月以内」が45%と、最初の1ヶ月がダイエットを継続するうえで最大の壁となります。
男女別では女性の方が「食事制限」で挫折しやすく、男性は「運動不足」で失敗しやすい傾向があります。年代別では、20代は“結果の早さ”を重視し、40代は“時間の確保”が最大の課題です。
続かないのは「脳の仕組み」が原因
私たちの脳は「即時報酬」を好むようにできています。
心理学でいうドーパミン報酬系は、「すぐに結果が出ること」に快感を感じます。
しかし、ダイエットは「すぐに成果が見えない」ため、脳がモチベーションを保てず、やがてやる気が低下します。
さらに、体にはホメオスタシス(恒常性維持機能)があり、急な体重変化を「危険」と判断して、体を元に戻そうとします。これが「リバウンド」や「停滞期」の正体です。
意志力の限界 ― ウィルパワーは使い切る資源
スタンフォード大学の研究によると、意志力(ウィルパワー)は消耗する資源であり、
1日の中で何度も我慢を繰り返すと、脳の前頭葉が疲弊して判断力が落ちることが分かっています。
短期集中!食事や運動管理でダイエットサポートします プロが7日間徹底サポート!リバウンドや挫折しない痩せ方を伝授
ダイエットが続かない8つの本当の原因
ダイエットを挫折してしまった人は「やる気が続かない」「気づいたら元に戻っている」と意志の弱さが原因だと感じる人が多いです。しかし、ダイエットが続かないのは、決して意志が弱いからではありません。
実は脳や心理、環境の仕組みが“ダイエットが継続できないようにできている”からです。ここでは、科学的に証明された「ダイエットが続かない8つの本当の原因」と、その具体的な対策を紹介します。
1. 脳の報酬系が働かない(即時報酬バイアス)
ダイエット最大の壁は、「努力してもすぐに結果が出ない」という現実です。
脳は「報酬(快感)」を得ることでやる気を出す仕組みを持っていますが、体重や体型変化のように成果が数週間後にしか現れない行動は、脳にとって報酬が“遅すぎる”のです。これを「即時報酬バイアス」と呼びます。
そのため、数日体重が変わらないだけで「無駄だった」と感じてしまうのは、脳の構造上、自然な反応です。
対策としては、小さな成果を“即時報酬”として可視化できるようにすることです。
たとえば、歩数・食事記録アプリを使って「今日は昨日より500歩多い」「スナック菓子を1回減らした」といった日々の努力や変化を見える化しましょう。これだけで脳が「達成感」という報酬を得られ、続ける力が生まれます。
2. 間違った目標設定
「2週間で5kg痩せる」「今月中にウエスト−10cm」――こうした目標設定は、一見モチベーションを高めるように見えて、実は続かない最大の原因です。
人間は「達成できなかった経験」を繰り返すと、自己効力感(自分にはできるという感覚)が低下してしまい、「どうせ無理」と諦めてしまうのです。
目標は「SMART原則」に基づいて設定しましょう。
具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、現実的(Realistic)、期限付き(Time-bound)であること。
たとえば、「1カ月で1kg減」「週に3回、夕食後に20分ウォーキング」など、無理なく達成できる目標がベストです。
3. 意志の力への過信
多くの人が「我慢すれば痩せられる」と信じています。しかし心理学の研究では、意志力は筋肉のように“使えば疲れる”ことがわかっています。
これを「自我消耗理論」と言い、我慢を重ねるほど意志のエネルギーは減少し、最終的に暴食や怠惰を招きます。
そのため、意志力に頼るのではなく「環境設計」でダイエットを自動化するのが効果的です。
たとえば、お菓子を見えない場所にしまう・エレベーターではなく階段が目に入る位置に移動する・夜はスマホの通知を切るなど、「意識しなくても正しい行動を選びやすい環境」を作ることがダイエットの継続&成功につながります。
4. 環境設計の失敗
行動経済学の「ナッジ理論」では、人は合理的ではなく、環境によって行動を左右されるとされています。
たとえば、健康的な食事を選びたいなら、冷蔵庫の一番見やすい位置に野菜やフルーツを置く。運動したいなら、玄関にスニーカーを出しておく。
こうした“軽い後押し=ナッジ”が、やる気よりも大きな効果を発揮します。
逆に言えば、環境設計を怠ると、日々の忙しさに流され、ダイエットは後回しになってしまうのです。
「意志」ではなく「仕組み」で動けるように、自分の行動を自然に導く環境づくりを意識しましょう。
5. 完璧主義
「1回間食したからもう終わり」「今日は運動できなかったから意味がない」――このような“白黒思考”は、ダイエット挫折の根源になりえます。
完璧主義の人ほど、少しの失敗を「すべて台無し」と捉え、続ける力を失ってしまいます。
そこで有効なのが“グッドイナフ思考(Good Enough Thinking)”。
「今日は7割できたからOK」「昨日よりマシなら成功」と考えるだけで、ダイエット継続のハードルが大幅に下がります。
6. 生理学的な反応
過度な食事制限をすると、体は「飢餓状態」と判断し、基礎代謝を落としてエネルギー消費を抑えます。
このように体が“省エネモード”に入ると、同じ食事量でも太りやすく、痩せにくい体になります。
重要なのは、カロリーを減らすことではなく、代謝を維持する食べ方をすること。
タンパク質をしっかり摂り、筋肉を減らさないPFCバランス(Protein・Fat・Carbohydrateの割合)を意識しましょう。
7. 一人で頑張ろうとしてしまう
ダイエットを一人で頑張ろうとすると人によっては非効率になってしまいます。
さらに、ハーバード大学の研究では、ダイエット経過を友人やSNSで共有したグループは、単独で行った人より継続率が2倍以上高いという結果が出ています。
人は「誰かに見られている」と思うだけで行動が変わる「社会的プレッシャー効果」を持っています。
また、自己流のダイエットは間違った方法になりかねません。
そこで、ダイエット&ボディメイクの専門家によるダイエットサポートがおすすめです!
オンラインダイエットサポート
- オンラインだから全国どこでもサポート!
- あなた専用の効率的ダイエットプランで理想の体に!
- ダイエットの専門家が毎日徹底サポート!
詳しくはこちら👉
8. 成果の可視化不足(セルフモニタリング)
努力しても成果が見えないと、脳は「意味がない」と判断し、やる気を失います。
だからこそ、セルフモニタリング(自己観察)が欠かせません。
体重・体脂肪率だけでなく、「歩数」「睡眠時間」「食事の写真」など、行動を記録していくことで、“成果の積み重ね”を実感できます。
アプリやノートに「できたこと」を書き出すだけでも、継続力は確実に上がります。
意志に頼らず続く!科学的に正しい7つのメソッド
ダイエットの成功は「強い意志」ではなく、「正しい仕組み」によって決まります。
人間の脳は、面倒・不安・誘惑に非常に弱い構造をしており、意思だけで行動を続けるのは不可能に近いのです。
ここでは心理学・行動経済学の研究に基づいた、“意志に頼らず続く”ための7つの科学的メソッドを紹介します。
https://bodymake-lab.net/how-to-lose-weight/
1. 習慣化の20秒ルール(ショーン・エイカー理論)
行動科学者ショーン・エイカーが提唱した「20秒ルール」
これは、「人は行動の開始に20秒以上かかると、継続率が大幅に下がる。」というものです。
逆に、行動を始めるまでの「20秒の壁」をなくすことで、習慣を自然に続けることができます。
実践方法
- 続けたい行動を「すぐできる場所」に置く(例:運動着をベッドの上に置く)。
- やめたい行動は「20秒の手間」を増やす(例:お菓子を棚の奥に入れる)。
- 習慣の導線を整える(例:朝起きたらすぐ水を飲む動線にボトルを置く)。
2. if-thenプランニング(実装意図の設定)
心理学者ピーター・ゴルヴィツァーの「実装意図理論(Implementation Intentions)」。
これは、脳は条件づけられた行動を自動化しやすいというもの。
「もし〇〇したら→△△する」と具体的に決めるだけで、実行率が2倍以上に上がる。
実践方法
- 「もし〇〇(状況)なら→△△(行動)」を3つ書く。
- 例:「もし昼食後に甘いものを食べたくなったら→白湯を一杯飲む」。
- 紙に書き、見える場所に貼る。
3. スモールステップの原理(1%改善法)
一文説明:
スモールステップの原理とは、行動心理学の「小さな成功体験(Micro Success)」効果のこと。人間の脳は成功体験を報酬として記憶し、行動を強化するというものです。
つまり、「いきなり完璧」ではなく、「1日1%の改善」で人は変わることができます。
実践方法
- 「やめる」ではなく「減らす」から始める。
- 例:「お菓子をゼロにする」→「1日1個まで減らす」。
- 習慣化したら、次の1%改善へ。
4. 記録の力(セルフモニタリング効果)
行動心理学の「セルフモニタリング効果」。これは、自分の行動を観察・記録すると、自己認識が高まり、無意識の行動が変化するというものです。
つまりダイエット中は記録をするだけで、行動が自然に改善されていきます
実践方法
- 食事・体重・運動など「1項目だけ」記録を始める。
- アプリやノート、写真どれでもOK。
- 週1回、記録を振り返る時間を設ける。
5. ソーシャルコミットメント
一文説明:
社会心理学の「アカウンタビリティ効果」。これは、人は他者に報告義務があると、行動の一貫性を保ちやすくなる。というものです。
そこで、ダイエットを始めるときは誰かに宣言しましょう。これだけで、ダイエットの継続率がアップします。
実践方法
- SNSや友人に「今週の目標」を宣言する。
- 毎週進捗を報告する。
- 失敗も正直に共有することで、支援を得られる。
6. 報酬設計
行動に「ご褒美」を設計すると、脳が自然にやる気を出してくれます。
これは、行動心理学の「オペラント条件づけ(行動強化理論)」というものです。
実践方法
- 成功した行動に小さな報酬を与える。
- 例:「1週間継続できたら新しい入浴剤」「3kg減ったら洋服を買う」。
- 報酬は“快楽より達成感”につながるものを選ぶ。
7. リカバリープラン(挫折を前提とする)
「失敗しない」ではなく「失敗しても戻れる仕組み」を作るようにしましょう。
これは、認知行動療法(CBT)の「リラプスプランニング(再発予防計画)」というものです。人は、失敗を想定すると、挫折後の回復スピードが格段に早まります。
実践方法
- 「つい食べすぎたときどうするか」を事前に決めておく。
- 例:「翌日は野菜多め+30分ウォーキング」。
- 自分を責めず、リズムをすぐ戻す。
無理せず継続できるダイエットで痩せるお手伝いします ノンストレスでリバウンドなし!二人三脚ダイエットサポート!
あなたのダイエット挫折タイプ
「続けるのが苦手」「またリバウンドしてしまった」
それは意志が弱いからではなく、“あなたの性格タイプ”に合っていない方法を選んでいるだけかもしれません。
ダイエット成功のカギは、自分の「挫折パターン」を知り、それに合った対策を取ること。
まずは、次のチェックリストで自分の傾向を診断してみましょう。
1. 完璧主義型
特徴:
何事もきっちり計画を立てたいタイプ。数字やスケジュール通りに進まないと強いストレスを感じます。
よくある失敗:
少しでも食べすぎたり運動をサボると、「もうダメだ」と極端に落ち込み、そこで全てを投げ出してしまう傾向があります。これを心理学では「オール・オア・ナッシング思考(白黒思考)」と呼びます。
対処法:
「100点を目指す」よりも、「70点でも続けられたら成功」と考える“グッドイナフ思考”を身につけましょう。
日記やアプリで「今日できたこと」を3つ書き出すだけでも、自己効力感(自分にはできるという感覚)が上がり、自然と前向きに続けられます。
2. 飽きっぽい型
特徴:
新しいことが好きで、同じメニューを続けるのが苦手。刺激がなくなるとすぐに飽きてしまうタイプです。
よくある失敗:
最初はやる気満々でも、数週間でモチベーションが低下。「また違う方法を試そう」と繰り返してしまう。
対処法:
単調さを防ぐ仕組みを作ったり、楽しめる工夫をするのがポイント。
例えば、週替わりで運動メニューを変える、食事のテーマを「和食週」「スープ週」などに分けてみましょう。
アプリやガジェットを使って進捗を「ゲーム化」するのも効果的です。飽きっぽい人ほど、楽しさを維持できる工夫をすることがダイエットを成功に導きます。
3. 情報過多型
特徴:
リサーチ好きで、最新の健康情報やSNS・YouTubeをよくチェックするタイプ。
よくある失敗:
あまりに多くの情報に触れるうちに、「糖質制限がいい?」「やっぱり16時間断食?」と迷いが増え、結局行動できなくなるパターン。情報の“取りすぎ”がブレーキになります。
対処法:
信頼できる情報源を1つに絞りましょう。
たとえば、「この管理栄養士の投稿だけ見る」と決めるだけで迷いが減ります。
また、実際に試す前に「これを2週間続けてみる」と期間を決めると、思考より行動が先に動きます。
4. 意志力依存型
特徴:
「気合と根性で頑張る!」という精神論タイプ。努力家ですが、疲れやストレスがたまると一気に崩れてしまう傾向があります。
よくある失敗:
「今日は我慢できた」「明日も耐えよう」と意志力で乗り切ろうとするため、ストレスが蓄積。ある日突然、暴食スイッチが入る。
対処法:
意志に頼るのをやめて、「環境を味方につける」こと。
お菓子を見えない場所にしまう、夜にスマホをリビングに置く、冷蔵庫の目立つ場所にカットフルーツを入れておく――こうした小さな環境設計が、自然に正しい行動を導いてくれます。
今日から始める!意志が弱くても続くダイエットプラン
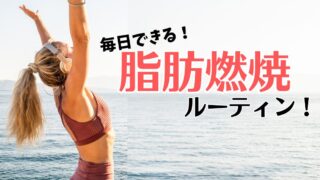
ダイエットで一番重要なのは継続させること。
しかし、この継続させることが一番難しい!
さらに、前述した通り、人間の脳や体変化することを嫌っているので、医師と関係なくダイエットを挫折してしまう原因となります。
そこで、今日から実践できるダイエット実践プランを紹介します。
【準備段階】10の環境設定チェックリスト
まずは、行動より「整える」ことから始めましょう。環境が変われば行動は自然に変わります。
以下の10個の中から無理なくできることを始めてみましょう!
- 冷蔵庫を整理し、加工食品や菓子を奥に移動
- テーブルの上にフルーツやナッツを置く
- 水筒を常備し「1日1.5〜2L」目安で水分補給
- 体重計・メジャーを目に入る場所に置く
- 睡眠時間を7時間確保するスケジュール設定
- スマホのホーム画面に「目標体重」ではなく「行動目標」をメモ
- お気に入りの運動ウェアを用意
- SNSで「一緒に頑張る仲間」をフォロー
- 冷凍庫にヘルシー食材(鶏むね肉、ブロッコリーなど)を常備
- 「食べすぎてもリセットできる」日常ルールを決める(翌日は軽く運動+水分多め)
【初日〜1週目】
行動経済学では「最初の1週間」が最も重要だとされています。
人のモチベーションは「新しいことを始める瞬間」に最も高く、ここで“成功体験”を積むと継続率が飛躍的に上がります。
簡単なもので大丈夫なので、1週間で毎日新しいことを始てみましょう!
例
- 1日目:体重・体脂肪・ウエストを記録(“現状を見える化”)
- 2〜3日目:朝食は抜かずしっかり食べる、特にたんぱく質を意識(卵・納豆・ヨーグルトなど)
- 4日目:無理なくできる運動を習慣にする(例:食後10分のウォーキングなど)
- 5日目:夕食を20時までに終える
- 6日目:1日1回、「今日できたこと」を1つでも良いので書き出す
- 7日目:1週間を振り返り、「継続できた行動」を書き出す
完璧を求めず、まずはダイエット習慣を継続することを一つの目標としましょう!
【2週目〜1ヶ月】習慣定着のための工夫
脳科学的には、新しい習慣が定着するまでに約21〜30日かかると言われます。
しかし、この時期は「飽き」「疲れ」「マンネリ」が出やすい期間になります。
そこで、無意識に行えるような行動の自動化がおすすめです!
小さなルーティンを積み重ねると、脳は「これが当たり前」と認識し、努力せずとも続けられるようになります。
例
- 朝起きたら水を飲む、夜は歯磨き後に間食をしないなど「行動連鎖」を利用
- 食事前に“5分間の食事記録”を取る(マインドフル・イーティング)
- 運動は「曜日固定制」(例:月・木・土は筋トレ)で決める
- モチベーションが下がったら、最初の写真や記録を見返す
【1〜3ヶ月】停滞期の乗り越え方
体が慣れてくる1〜3ヶ月目は、多くの人が「体重が減らない…」と焦る時期です。
しかし、ここでやめてしまうのはもったいないです!これは“生理的適応期”であり、筋肉量が増え代謝が整う重要な段階で、所謂『停滞期』と呼ばれる期間です。
停滞期は以下のような工夫をすることが大事です!
- 体重ではなく「見た目」や「体脂肪率」で評価する
- 食事内容を一度見直し、たんぱく質量を再確認
- 軽い“変化”を入れる(運動時間を5分延ばす、間食を1回減らす)
- 「停滞期=成功の前兆」と意識を切り替える
【3ヶ月以降】習慣の維持と発展
3ヶ月を超えると、体も心も「新しいライフスタイル」を受け入れ始めます。
ここからは“維持”ではなく、“アップデート”の段階です。
アップデート例
- 目標を「数字」から「生き方」に変える(例:体重より“軽やかに動ける自分”)
- 週に1回「チートデイ」ではなく「リフレッシュデイ」を設定
- 新しい挑戦を加える(登山・ダンス・ヨガなど)
- 他人との比較ではなく、「昨日の自分」と比べる
脳は“楽しみながら続ける行動”を自動化します。
だからこそ、苦しむより“心地よい努力”を続けることが、最も効率的なダイエット法なのです
第6章:よくある質問Q&A
Q1:モチベーションが下がったときの対処法は?
やる気やモチベーションが下がったときは「原因」ではなく「結果」に注目しましょう!
人間の脳は、行動してからモチベーションが生まれるという仕組みがあります。
まずは“1分でできる行動”をしてみましょう。その場でスクワット3回や家の周りを一周歩くでもOK。小さな成功が次の行動を呼び起こします。
Q2:停滞期はどう乗り越える?
停滞期は体が慣れてエネルギー効率を上げている証拠です。
体重が落ちにくいだけで、体内では脂肪を燃える体質へと再構築が進んでいます。
焦らずに、食事、運動、睡眠の見直しましょう!
Q3:リバウンドを防ぐには?
ダイエット中にダイエット終了後も続けられるような、「日常に溶け込むダイエット習慣」を身に付けましょう。
たとえば、お菓子を買い置きしないようにしたり、なるべくノンオイルの食品や調味料を選ぶなど、行動経済学の“ナッジ理論”のように、無意識でも正しい選択ができる環境を整えましょう。
Q4:忙しくて時間がない人向けの方法は?
毎日の移動時間や食事の種類を工夫するのがおすすめです!
駅やオフィスでは積極的に階段を使う、最寄り駅より一つ手前で降りて歩いて帰る、ランチは和食を選ぶ、主食を玄米に変えるなど、忙しくても日々の生活の中で痩せられるポイントはたくさんあります!
Q5:何度も挫折している人でも大丈夫?
むしろ“挫折経験がある人”こそ成功のチャンス!
脳は失敗を通して学習します。大切なのは「過去のやり方を繰り返さないこと」。
前回のダイエットの挫折の理由を洗い出しましょう!
また、“意志力ではなく仕組みで続ける”を意識しましょう。
まとめ
続かないのは意志の弱さではなく、仕組みの問題
約87%がダイエットに挫折すると言われていますが、それは意志が弱いからでも「根性が足りないからでもありません。
人間の脳は変化をストレスと認識し、現状維持を好むようにできています。
そのため、脳科学的に見れば、ダイエットは続かないのが普通です。
だからこそ、ダイエットを成功させるためには継続できる仕組みを作ることです。
今回紹介した「科学的に正しい7つのメソッド」や「意志が弱くても続くダイエットプラン」を参考にしてダイエットを頑張ってみて下さい!
しかし、一人でのダイエットは挫折しやすくリバウンドしやすいです。
そこで、専門家によるダイエットサポートもおすすめしています!
オンラインダイエットサポート
- オンラインだから全国どこでもサポート!
- あなた専用の効率的ダイエットプランで理想の体に!
- ダイエットの専門家が毎日徹底サポート!
詳しくはこちら👉